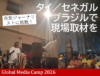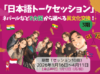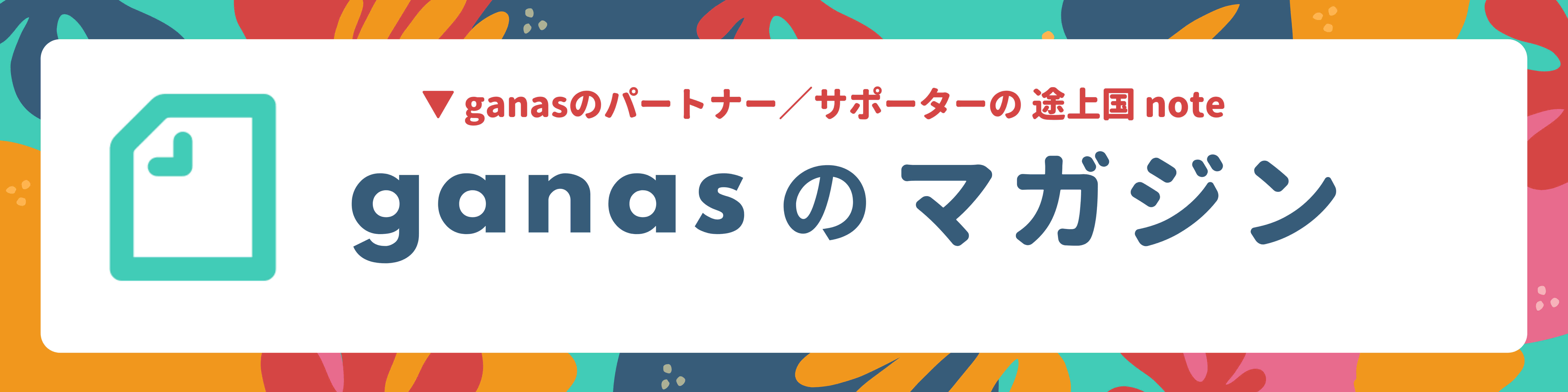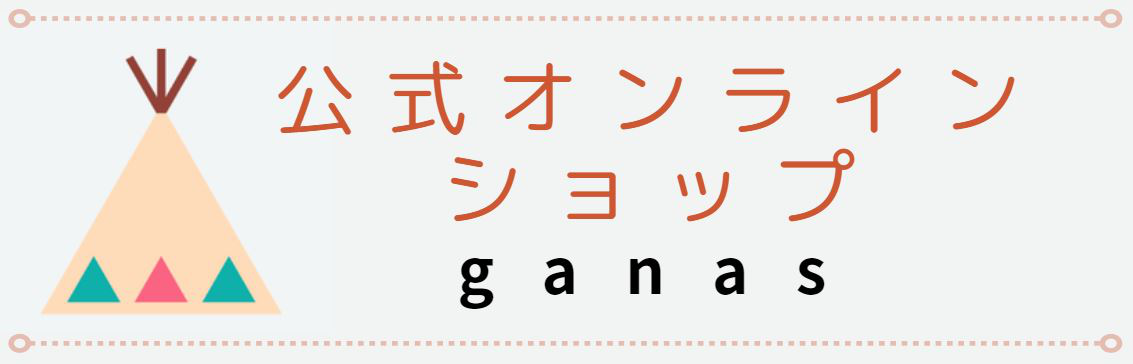タイ・チェンマイのアパートでパソコンに向かうミャットさん。取材は電話を使う。土日もなく書き続ける彼にとっての息抜きは同胞とのトレッキング(チェンマイの周りには山がある)。取材の最後に「僕を拷問した警官に、なぜこんなことをしたのか、と理由を聞いてみたい」と語った
タイ・チェンマイのアパートでパソコンに向かうミャットさん。取材は電話を使う。土日もなく書き続ける彼にとっての息抜きは同胞とのトレッキング(チェンマイの周りには山がある)。取材の最後に「僕を拷問した警官に、なぜこんなことをしたのか、と理由を聞いてみたい」と語ったムスリムはパスポート作れない
ミャットさんは2021年11月19日、突如釈放された。「僕は武器を所持していたわけでもないし、また刑務所の中も、軍が拘束した人でいっぱい。おそらく優先的に出してもらえたのだろう」と推測する。
ミャットさんの容疑についての裁判は結局、公判が5回ぐらい開かれただけで中途半端な形で終わった。
ただミャンマーでは釈放されても再び捕まるケースは珍しくない。ミャットさんはダウェイで1カ月にわたって、タニンダーリ管区(ダウェイはその中心都市)を主にカバーするメディアのインターン・ジャーナリストをやりながら、見つからないよう実家に帰らず居場所を転々とした。
その後、仲間のつてをたどってミャンマーの最大都市ヤンゴンへ行く。ダウェイでは反政府リストに載っているため、やはり危ないと判断したからだ。
ヤンゴンでミャットさんはプロのジャーナリストとして記事を書き始める。命の危険は承知の上。「僕の仲間には民主派の軍事組織である国民防衛隊(PDF)に入り、兵士として国軍と戦う人もいる。僕のやっていることはそれに比べたらやさしいこと」
ヤンゴンでも、国軍に居場所を知られないよう転々とした。だが危険すぎると思い、半年後、国を出る決意をした。
だがミャットさんはイスラム教徒(ムスリム)。パスポートを作るのは困難だ。また、ミャンマー人にとって基本の身分証明書である国民登録カード(NRC)も逮捕されたときに没収されたまま。再発行してもらうには日本円で10万円以上かかる。
ミャットさんに残された選択肢はタイへの不法入国。ヤンゴンからモン州に下り、タイのカンチャナブリへと渡った。そこに1年滞在。スマホを使い、ミャンマー国内のミャンマー人を取材し、記事を書き続けた。
その後、ミャンマーの亡命メディアで活動するジャーナリストのコミュニティがあるチェンマイへ。1年半前からアパートを借りた。現在はタイの一時滞在許可証(ピンクカード)も取得した。
ミャットさんの現在の月収は1万2000バーツ(約5万4700円)。このうち、電気代などを含む家賃に4500バーツ(約2万500円)を払う。生活はギリギリだ。
「貯金はできない。もちろん病院にも行けない。ピンクカードの更新にもお金は必要。徴兵制の対象(18歳以上)になった弟を故郷から呼び寄せたいけれど、いまの状況では難しい」と悩みを打ち明ける。
米国の援助停止で存亡の危機
ミャットさんの月収は実は最近、下がったという。以前は1万5000バーツ(約6万8300円)もらっていたから2割カットされた計算になる。
ミャンマーは軍政による厳しい報道規制があるため、ミャンマーの現状をストレートに伝えられる亡命メディア(国外に拠点をもつメディア)の存在は不可欠だ。ミャンマーの亡命メディアの数は、スタッフ数人の小さなところも含めると20ぐらいはあるといわれる。
ただミャンマーの亡命メディアの経営はどこも厳しい。ミャットさんは「(米国のトランプ大統領が米国の援助機関である国際開発庁<USAID>を解体したことで)間接的にもらっていた米国からの支援がストップしたこともかなり響いていると聞く」と説明する。
ミャットさんが勤務する亡命メディアは実際、スタッフの数を10人から5人に減らした。ミャンマー人ジャーナリストにとってはいつまで仕事を続けられるのか、不安が募っていく。
そうしたなか、ミャットさんは最近、ミャンマーのダゴン大学の女子大生についての記事を1本書いた。彼女は民主化運動の学生リーダーだった。拘束された後、性器を蹴られたり、タバコの火をつけられたり、と70時間にわたる拷問を受けた。この女性はその4年後に死んだ。
「この記事を書いた後、自分の体験がフラッシュバックして涙が止まらなかった。夜寝ていたら、トラウマが悪夢として現れてきた」(ミャットさん)
自らの生活もままならない現実、トラウマとの闘い。それでもミャットさんは書くことはやめたくないと力を込める。
「正直言って、ミャンマーが3~4年以内に民主主義を取り戻すとは思えない。だけど、僕が書かなかったら、自分と同じように、人生を大きく狂わされた人の壮絶な体験を知る術がなくなる。彼らの声を聞きたい。それを発信したい」