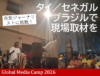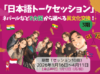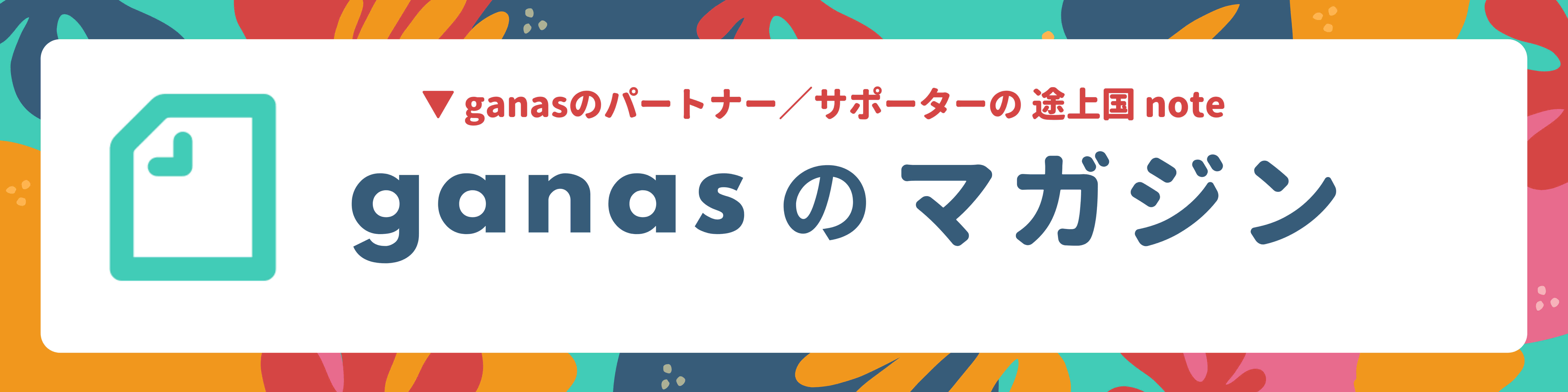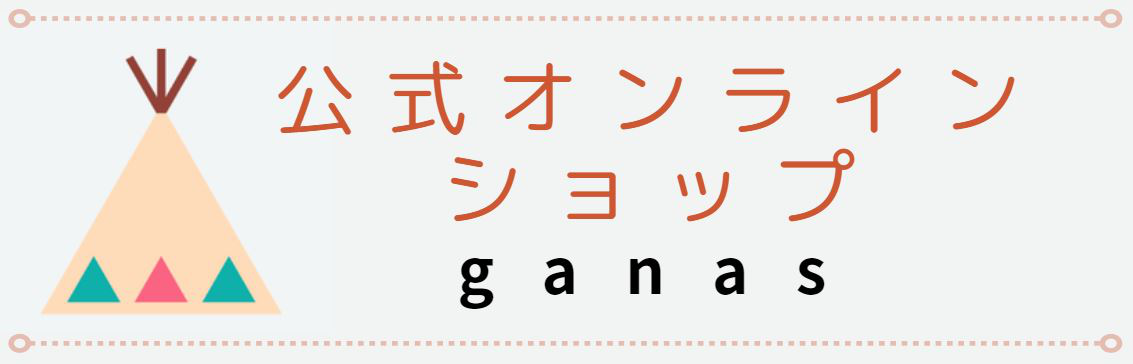タイ・チェンマイのアパートでパソコンに向かうミャットさん。取材は電話を使う。土日もなく書き続ける彼にとっての息抜きは同胞とのトレッキング(チェンマイの周りには山がある)。取材の最後に「僕を拷問した警官に、なぜこんなことをしたのか、と理由を聞いてみたい」と語った
タイ・チェンマイのアパートでパソコンに向かうミャットさん。取材は電話を使う。土日もなく書き続ける彼にとっての息抜きは同胞とのトレッキング(チェンマイの周りには山がある)。取材の最後に「僕を拷問した警官に、なぜこんなことをしたのか、と理由を聞いてみたい」と語ったミャンマー南部のダウェイで拷問を受け、投獄されても、不屈の闘志で記事を書き続けるジャーナリストがいる。タイ・チェンマイ在住のミャットさん、29歳だ。壮絶な体験をもつ彼は「(民主化を求めるというよりも)軍政に人生を狂わされた人たちの姿を伝えたい。自分が書かなきゃだれが書く」と熱く語る。
頭脳で拷問を乗り切る
ミャットさんの人生を一変させたのは、4年半前(2021年2月1日)にミャンマー国軍が起こしたクーデターだった。
ミャットさんは当時、タニンダーリ管区のダウェイに住んでいた大学生。土木工学を勉強していた。「民政がひっくり返されていなかったら、間違いなく僕は土木エンジニアの仕事をしていたと思う」と振り返る。
ミャットさんは軍事クーデターが起きた後、民主化の回復を求めるデモ隊の学生リーダーとして、抗議デモをゲリラ的にさまざまな場所で企画したり、参加したりし始める。と同時に、フリーランスの市民ジャーナリストとしてもバイクにまたがり現場へ行き、デモの写真を撮っていた。
ところが5月に突然、拘束される。ミャットさんにかけられた容疑は刑法505条aとc(反乱を扇動すること、または「恐怖をもたらすこと」を意図した表現をすること)と同145条(許可なく集会やデモを行うこと)。ミャットさんと一緒に13人の学生仲間が捕まったという。
「僕はダウェイ出身。ダウェイをよく知っているから(軍人や警官の勤務地は常に変わるので、ダウェイ出身者はほぼいない)、捕まらないと油断していた。ただ軍人は私服を着ていて、わからなかった」
拘束されたとき銃で頭をガツンと叩かれたミャットさんは近くの警察署へすぐに連行された。スマートフォンや国民登録カード(NRC)は没収。手は後ろで縛られ、足には鎖がかけられた。
軍人、警官、捜査当局の職員の3人から尋問、いや拷問が始まる。銃口を向けられた状態で、スマホの中に映っていたデモ参加者らの写真を見せられ、「この人物はだれだ?」「どこにいるんだ?」「何をしているんだ?」とミャットさんを問い詰める。
答えないと、木の棒で激しく殴打される。ミャットさんが履いていた靴を脱がされ、それで顔を繰り返し思いっきりひっぱたかれた。
尋問(拷問)で命を失った人も少なくないことをミャットさんは知っていた。恐怖で凍り付いた。「早く終わってくれ」と祈りながら、ひたすら耐えるしかなかった。
ただミャットさんの頭は冷静だった。拷問を少しでも和らげようと必死に考えを巡らせた。「家宅捜索がすでに入った仲間の情報については軍や警察も把握しているはず。だからそこは正直にしゃべった」。すると信用されたのか、20時間で拷問は終わった。
殺人犯・レイプ犯と同じ部屋
拷問をなんとかやり過ごしたミャットさんは刑務所に送られた。収容される前に新型コロナウイルス感染症の検査を受けたところ、結果は陽性。近くの公立病院に「囚人のセクション」があり、そこに1カ月入院させられることに。退院後、ダウェイの刑務所に入れられた。
ダウェイ刑務所には当時1000人ほどが収容されていた。政治犯はうち300人程度。政治犯の多くは、ミャットさんのように、抗議デモにかかわったり、民主化の象徴であるアウンサンスーチー氏が好んだ花の髪飾りの写真をフェイスブックに上げたりした人たちだった。
ミャットさんが入れられたのは教室ぐらいの広さの部屋。ここで40~50人が寝る。ベッドはなく、ブランケットの上に寝た。収容される人がどんどん増えていき、最後はあおむけで寝るスペースはなかった。横になって眠ったという。
同じ部屋にはレイプ犯や殺人犯などの凶悪犯もいた。狭い部屋に大人数が押し込まれていることもあって、ストレスを抱えた男たちが殴り合いのけんかをすることも。「映画のように部屋にはボスがいた。態度が気に入られないと巻き込まれるので、目を付けられないよう気を配った」(ミャットさん)
食事は、朝は具のない焼き飯、昼はコメとひよこ豆のヒン(煮込み)、夜は日によって変わるが鶏肉や魚、卵とカボチャの葉っぱのスープなどが出た。「塩を使っていないので、どれも味がしなくて食べられなかった」と言う。
差し入れは1週間に1回認められた。ミャットさんの母が干し魚を持ってきてくれた。だが看守に奪われることもざらだった。
水浴びは毎日できた。ただし許された時間は1回わずか1分。同時に服も洗濯する必要がある。「不潔になると肌がかゆくなる。これに最も悩まされた」(ミャットさん)
刑務所ではまた、「訓練」もあった。国軍の幹部が時折やってきては、受刑者に6時間にわたって同じ姿勢でじっと座ることを強要した。
息抜きとなったのは、民主化運動で捕まった仲間と話をしたり、刑務所内にあった小さな図書館で本を読んだりすること。1日に2時間ぐらい自由時間があった。
生き地獄だった20時間の拷問と半年の刑務所暮らし。それでもミャットさんは「民主化運動にかかわったことに後悔はまったくない」と言い切る。