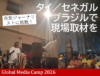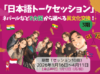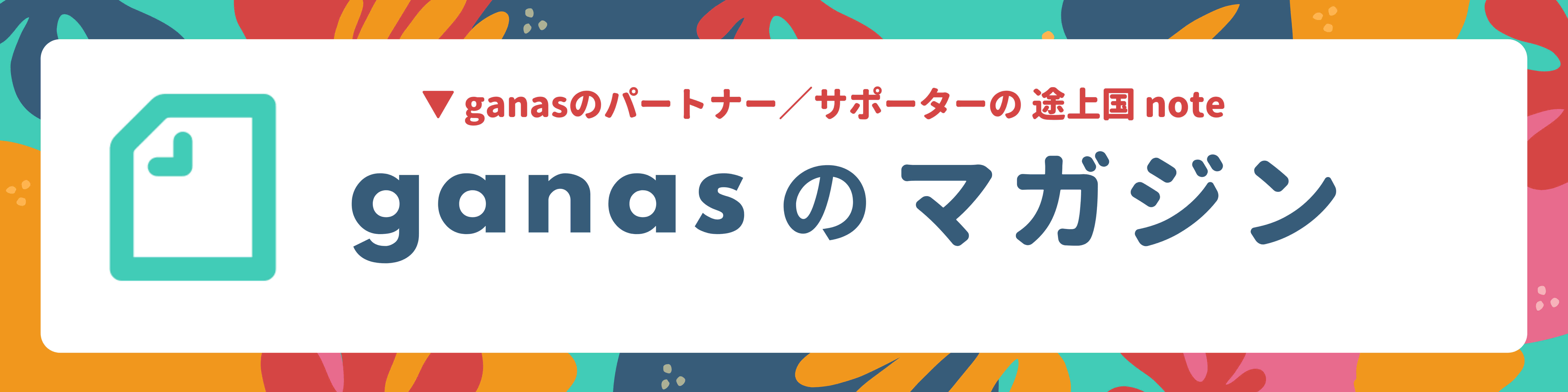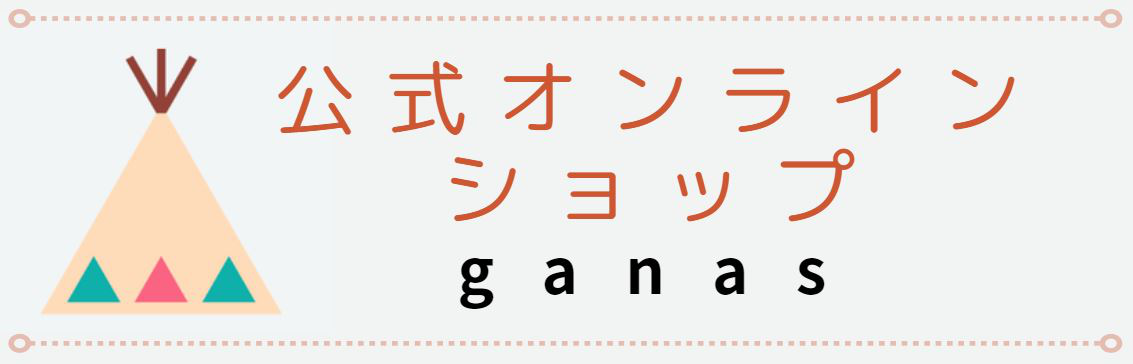コロンビアの国内避難民とその子どもたちを支援するNGOコアパスの代表を務めるサンドラ・プエルトさん。「きょうはインタビューを受けるのが楽しみ」。エステサロンを経営する娘に前日、マツエク(つけまつ毛)を仕上げてもらい、目力ましまし、気合い十分で熱く語ってくれた
コロンビアの国内避難民とその子どもたちを支援するNGOコアパスの代表を務めるサンドラ・プエルトさん。「きょうはインタビューを受けるのが楽しみ」。エステサロンを経営する娘に前日、マツエク(つけまつ毛)を仕上げてもらい、目力ましまし、気合い十分で熱く語ってくれた「自分の大切な“子どもたち”を守るためにやりたいことがある」。こう力を込めるのは、50年以上続いたコロンビア内戦の国内避難民とその子どもたちをアンティオキア県メデジン郊外の貧困地区アヒサルで支援するNGOコアパスの代表を務めるサンドラ・プエルタさん(48歳)だ。10年にわたるアヒサルで支援してきた経験から、「子ども食堂」や「子どもの遊び場」を作る新たな計画をあたためている。
無給で働く、娘から生活費の支援も
コアパスの現在の主な活動は、子どもたちが本に親しめる「子ども図書室」の運営と教育的なイベントの開催だ。
子ども図書室の利用は無料。だが利用するにはカンやビン、ペットボトル、段ボールなどのごみを持ち込む必要がある。それらはリサイクル業者に引き取ってもらい、コアパスの活動資金にする。
ただ金額は雀の涙だ。「3カ月集めて20万ペソぐらい(約8000円)。財団や企業からの寄付があるけれど、活動するにはもっともっとお金が必要ね」とサンドラさんは語る。無給で働くサンドラさんは自分の食い扶持を得るため、さまざまな仕事を掛け持ちする。またエステサロンを経営する娘から、生活費の援助を受けることも。
それでも彼女には実現したい構想がある。それは、「子ども図書室」も含めた“子ども村”を広げることだ。
構想の目玉となるのが、「子ども食堂」。40人ぐらいを対象に無料で週5日、栄養のある昼食を提供する。アヒサルの子どもたちの栄養状況を少しでも改善するのが狙いだ。
もうひとつは「子どもの遊び場」を作ること。「子どもたちは危険な斜面や下水が流れ込む川辺で遊んでいる。安全な環境で遊ばせたい」とサンドラさんは言う。
よく食べ、よく遊び、よく本を読む。この3つが土台となって、「頑張って勉強し、自分のことを自分で守れる大人になってほしい」とサンドラさん。「いまは独身の私にとって、アヒサルの子どもたちは私の家族みたいなもの。みんなの力になりたい」と意気込む。
夫が内戦で殺され、国内避難民に
現在は助ける側のサンドラさんだが、実は壮絶な過去の持ち主だ。
コロンビア内戦の被害者でもあるサンドラさんは激戦地のひとつアンティオキア県ウラオで生まれ育ち、結婚もした。ところが夫は内戦の犠牲に。「娘を妊娠しているとわかったのは夫が殺された後」。辛い経験だったが、娘と自分を守るため、13年前の2012年にコロンビア第2の都市メデジンに避難した。
着の身着のままウラオを脱出し、落ち着いたのはメデジン北部のベジョ。シングルマザーで生活は大変だったが、避難民などを支援するコアパスの活動に参加した。そこで避難民が行政のサポートを受けるには法律の知識が必要だと痛感したサンドラさんは法律を学びたいと思い始める。そんな折、コアパスの当時の代表から紹介を受け、地元の有力者が学費を出してくれることになった。
サンドラさんはメデジンに隣接するイタグイの大学に法律を学ぶため入学した。同じころ、新しいパートナーとの出会いもあった。彼と娘と3人での暮らしがスタートした。
コロンビアの大学の朝は早い。6時に始まる授業に間に合うようにするため、毎朝4時に起床。家族の朝食と昼食を用意し、5時にメトロに乗って通学。昼過ぎまで大学の授業を受け、その後は、コアパスのアヒサルでの活動を手伝い、夕方自宅に戻る。
パートナーは家計を支えるため働きに出るかたわら、当時中学生になっていた娘と協力して掃除、洗濯といった家事を担い、サンドラさんの学業を支えてくれた。「平日は大学と活動で時間がなく、週末にまとめて大学の課題に取り組んだ。でもアヒサルでの活動も、大学で学ぶことも私にとってとても大切な時間だった」とサンドラさんは振り返る。

メデジン郊外の貧困地区アヒサルにコアパスが作った子ども図書室