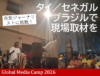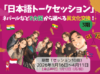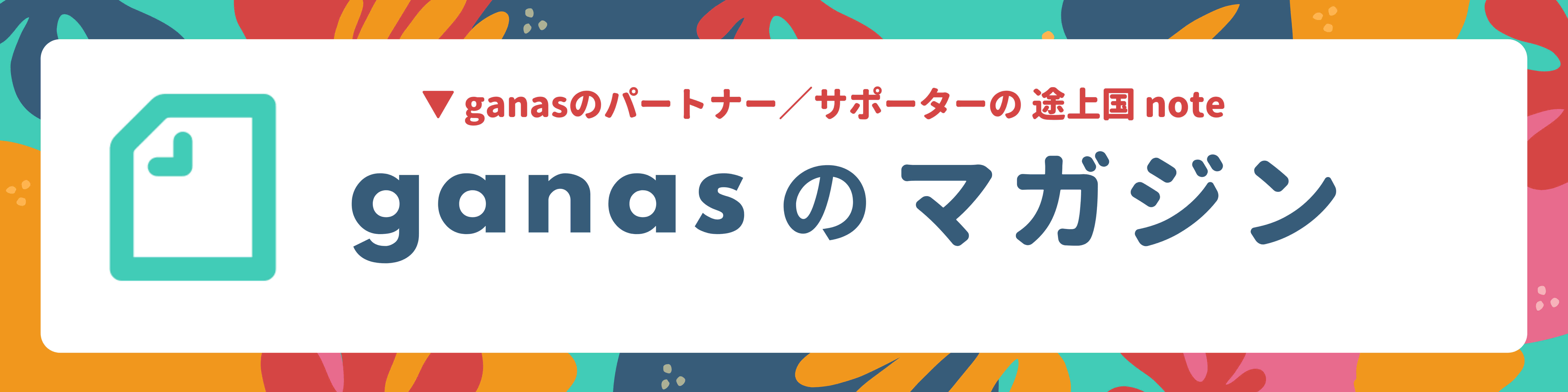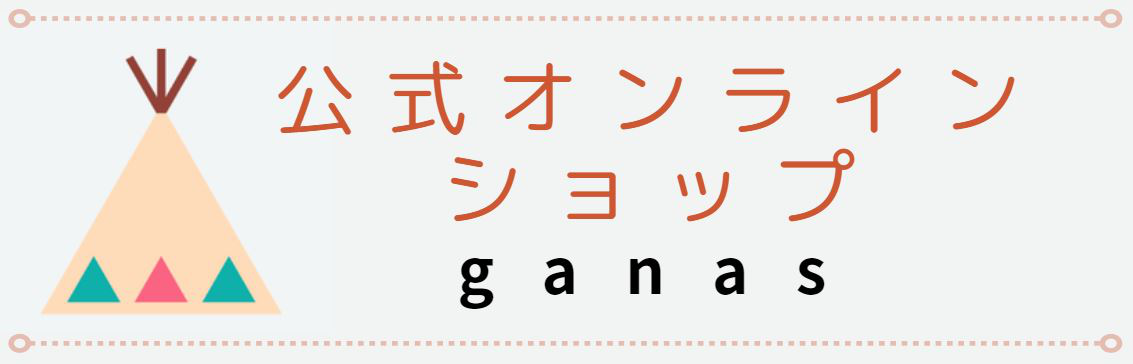林達雄(はやし・たつお)氏プロフィール: 1954年横浜市生まれ。医師。1983年よりタイとエチオピアで緊急救援活動に従事。日本国際ボランティアセンター(JVC)代表、アフリカ日本協議会(AJF)代表を歴任し、2000年からはエイズ問題に取り組む。現AJF特別顧問。日本とアフリカをつなぐ市民ネットワークの構築や政策提言に携わり、黎明期にあった日本の国際協力の発展に尽力。著書『エイズとの闘い』(岩波ブックレット)
林達雄(はやし・たつお)氏プロフィール: 1954年横浜市生まれ。医師。1983年よりタイとエチオピアで緊急救援活動に従事。日本国際ボランティアセンター(JVC)代表、アフリカ日本協議会(AJF)代表を歴任し、2000年からはエイズ問題に取り組む。現AJF特別顧問。日本とアフリカをつなぐ市民ネットワークの構築や政策提言に携わり、黎明期にあった日本の国際協力の発展に尽力。著書『エイズとの闘い』(岩波ブックレット)「1970年代の日本には、NGOという単語もなかったけれど、生きる道を探していたら、アフリカにたどり着いていた」。こう語るのは、1983年から医師としてタイとエチオピアで救援活動をし、現在はアフリカ日本協議会(AJF)の特別顧問を務める林達雄氏(70)だ。2000年にエイズを治療するジェネリック薬の輸入・製造を求める国際キャンペーンに参画し、2005年には世界的な市民運動となった「貧困と闘うグローバルキャンペーン(GCAP)」の日本側の代表者を務めた林氏の半生を連載する。
死にたかった
林氏は1954年、横浜で生まれた。小学生のとき、祖父が自死した。第二次世界大戦に出兵したらしいが、原因は不明。うつの症状があったらしい。
「子どものころから生きるのがつらかった」と林氏は振り返る。時代は高度経済成長に突入していくころ。子どもは明るく元気であるべきといった世の中の空気が息苦しかった。
小学校では休み時間になると、校庭で元気に遊ぶクラスメイトたちを横目に、教室の隅にある本棚から、お気に入りの本を取り出しては読みふけった。ダーウィンが世界を一周し、各地で観察したさまざまな生き物について書いた『ビーグル号航海記』。知らない世界に憧れる、夢見がちな少年だった。
心がなぜつらいのか、自分でもわからなかった。耐えかねて、母に「死にたい」と打ち明けた。母の答えは「あんたが死ぬなら私が死ぬ」だった。
次第に、「心」に惹かれるように。心理学者の河合隼雄がユング心理学を日本に持ち込んだころだった。高校生の林氏はユング心理学の本を貪るように読み、その先に精神科医になることをイメージするようになる。母方の おじ2人が医師でもあり、医師は身近な職業だった。
心理学だけでなく、虫や植物を観察するのも好きだった。高校の部活動は生物部。生態学(エコロジー)を学ぼうと東京大学理科2類を受験するも不合格。一念発起して、翌年は精神科の医師を目指して愛媛大学医学部を受けて合格した。医師としての道筋が見えてきた。

クラスメイトと遊ぶ10歳頃の写真。右端のマッシュルームカットの少年が林氏(写真は林氏から提供)