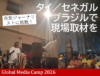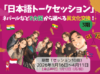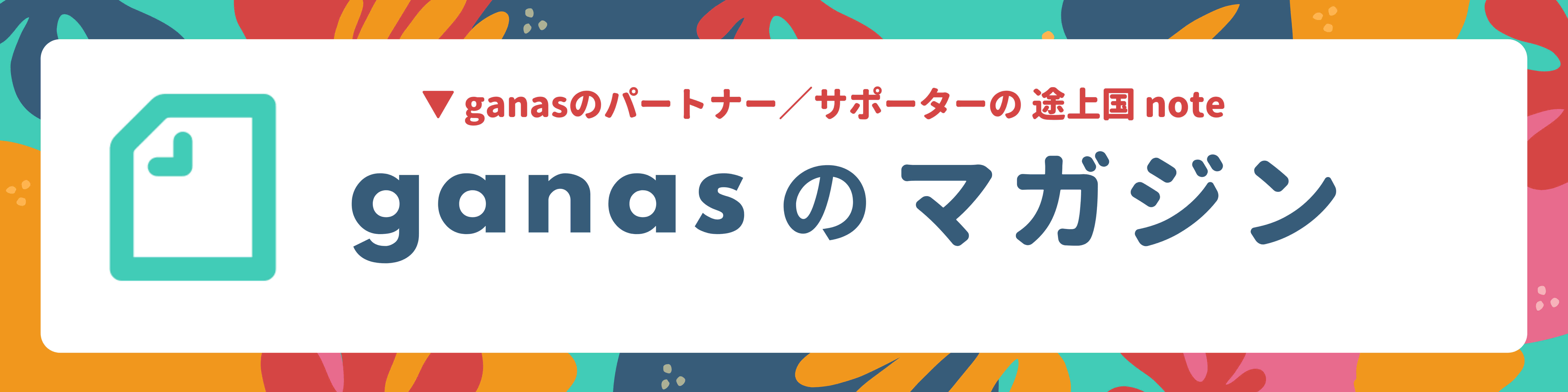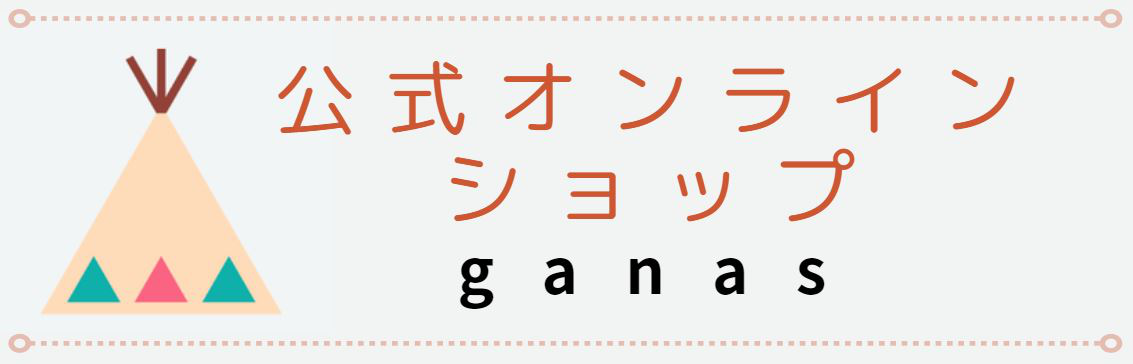ベネズエラ難民のグラフィラ・ラボリスさん(右)。弾けるような笑顔が印象的だった。コロンビア・メデジン近郊のアヒサルの家で撮影
ベネズエラ難民のグラフィラ・ラボリスさん(右)。弾けるような笑顔が印象的だった。コロンビア・メデジン近郊のアヒサルの家で撮影水道から水が出るのも、電気が来るのも週にわずか2時間程度。夜通し並んでも手に入るのは主食のトウモロコシの粉一袋――。そんなベネズエラの暮らしから抜け出そうとコロンビアへ逃れたベネズエラ難民がいる。グラフィラ・ラボリスさん、45歳だ。彼女は8年前から、子どもや孫とともにメデジン近郊の貧困地区で新たな暮らしを始めた。
ベッドの脚まで燃やす
ラボリスさんはカラカスで5人の子どもと暮らしていた。生活は過酷だった。
「水も電気も来るのは週に2時間。電気がなければろうそく、料理するときに使うガスがなければベッドの脚やプラスチックのコップまで燃やした」とラボリスさんは振り返る。
食べ物もろくに手に入らなかった。スーパーマーケットが開店する前、夜中から並んでもトウモロコシの粉一袋しか買えないことも。さらに国民IDカードの番号の末尾によってはせっかく並んでも購入できないことすらあったという。
1日の食事の回数は1~2回。キャッサバばかりで、油はほとんど手に入らなかった。鶏肉を食べられるのは週に1度、カラカスは海に近いこともあってイワシは3度ほど。子どもたちは学校に行けても「お腹が空いてどうしようもないから、行かない日も多かった」とラボリスさんは語る。
医療も崩壊していた。ラボリスさんの母は卵巣の手術を受ける必要があったが、ベネズエラではメスやガーゼなどの器具や薬剤をすべて自分で調達しなければならない。ハイパーインフレ(2016年のインフレ率は254%。ピークは2018年の6万5000%)も手伝って、費用は10万ドル(現在のレートで約1460万円)にのぼった。国外に住む親せき30人が手分けして送ってくれたお金で「なんとか手術できた」と説明する。
食べ物と医療で限界を感じたラボリスさんは9年前(2016年)、ベネズエラを脱出する決意をした。
カラカスから、コロンビアとの国境の町サンクリストバルまではバスで十数時間。バスターミナルで夜を明かし、翌日、コロンビア側のククタへ渡る。両国のイミグレーションの間は25分歩く。「出国するベネズエラ人が押し寄せ、殺気立っていた」と振り返る。
ベネズエラ側のイミグレーションを通るとき、ベネズエラ国旗のタグや黄・青・赤の国旗色をあしらったかばんは持って出ることが許されなかった。「ベネズエラを去るなんて祖国に対する愛情が足りない」と難癖をつけられる。
「コロンビアのククタに着いたら、すぐに水と食料をもらえた。病気がないかの医療チェックも受けられ、驚いた」(ラボリスさん)。ククタのバスターミナルの椅子で寝て、翌朝、コロンビア第2の都市メデジンへバスで向かった。バス代は、パナマに逃れた親せきが送ってくれた。カラカスからメデジンまで丸3日かかった。

ラボリスさんの自宅の壁には家族の写真が所狭しと飾ってある