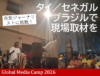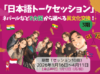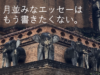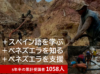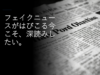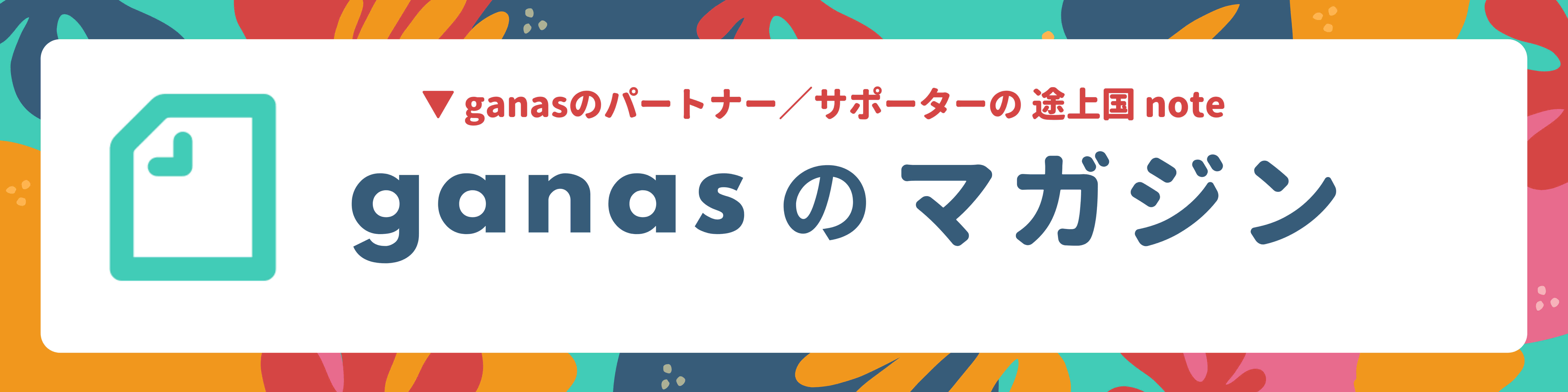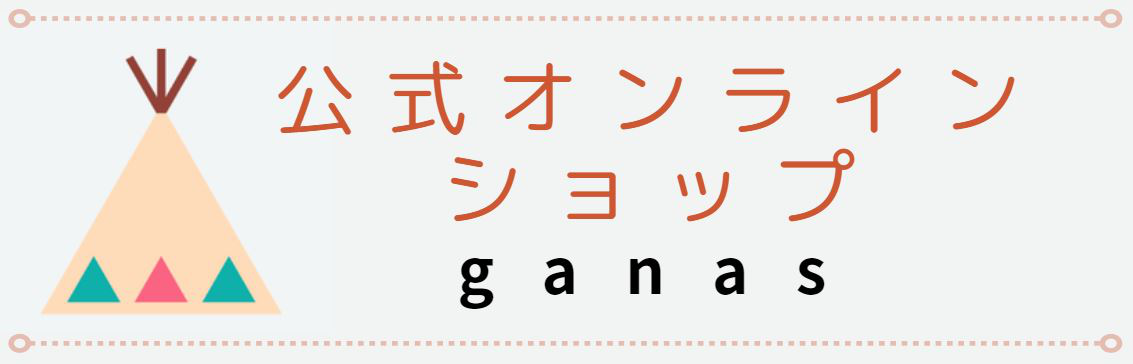小型のレントゲン撮影機を使ってカンボジア難民のレントゲンを撮るようす。難民キャンプ内の村を毎日3カ所ほど巡回した。レッドヒル難民村で。写真は日本国際ボランティアセンター(JVC)提供
小型のレントゲン撮影機を使ってカンボジア難民のレントゲンを撮るようす。難民キャンプ内の村を毎日3カ所ほど巡回した。レッドヒル難民村で。写真は日本国際ボランティアセンター(JVC)提供念願かなって、タイ東部のサケオ県にあるカンボジア難民キャンプで1983年から国際協力NGO日本国際ボランティアセンター(JVC)の医師として働き始めた林達雄氏。他国の援助メンバーたちと毎週のように飲んで踊って青春を謳歌していた。ところが、難民に配る物資が裏で、カンボジア国民を大量虐殺しているポル・ポト派に流れているのを知る。「援助することが逆に紛争を長引かせているのかもしれない」と気持ちがざらついた。(第1回はこちら)。
早くタイで就職したい
うつ症状に悩んだ林氏が1980年にタイの村にやすらぐ場所を見つけてから3年。難民キャンプに医師として派遣されるまでの道のりは実にスムーズだった。
愛媛大学医学部6年生の林氏は、はじめ自らの心の不調をきっかけに精神科医を目指していた。それがサケオ県アランヤプラテートにある難民キャンプで、地雷を踏んで足を失ったカンボジア人たちを治療する現場を見たことで、外科医になろうと心変わりする。
大学を卒業し医師免許を得てから2年間は、横浜の国立病院で臨床研修医となった。ポケベルで夜中に何度も呼び出された。緊張した毎日に疲れて、気分が落ち込むように。林氏は早くタイで就職したいと思った。「1982年当時は海外で働ける場所を探すのは簡単ではなかった」(林氏)
思いあまった林氏は、外務省の国際協力局に電話をかけてみた。担当者が「JVCがタイの難民キャンプに行ける医師を募集している」とあっさりと教えてくれた。
ちなみにJVCは、インドシナ難民を支援するために、日本の若者が1980年にタイで創設した日本の草分け的なNGOだ。その中心となったのが、国際協力機構(JICA)が派遣する青年海外協力隊(現在のJICA海外協力隊)の1期生(派遣国:ラオス)だった星野昌子氏だ。
林氏は、「JVCの対応はすごく良かった。外務省に紹介してもらったからかも。その時にJVCで働きたいと強く思った」と振り返る。
タイ行きが決まった。父は反対したが、母はあなたの人生だからと背中を押してくれた。研修生仲間は、壮行会を開いて送り出してくれた。
たぎる使命感はなかった
林氏が、タイ国境のカンボジア難民キャンプで医療支援を始めたのは1983年4月だった。ベトナム軍がカンボジアに侵攻したことでポル・ポト政権は1979年1月に崩壊。内戦の混乱が続くなか、カンボジアからタイへ逃げる難民は最大期には45万人に達した。
難民キャンプには3派連合(ポル・ポト派、王党派、ソン・サン派)と呼ばれる各勢力が難民にまぎれて流入。林氏が現地入りしたのは、国際援助がはじまり難民の数が20万~25万人と推測される頃だった。
朝8時、林氏はレントゲンの装置を載せたトヨタ・ランドクルーザーにタイ人のレントゲン技師と乗り込む。2カ所ほどの検問所でチェックを受け、砂ぼこりをあげながら車は難民キャンプへ。このころのタイは乾季だ。舞い上がった土で難民キャンプは全体に茶色くくすんでいる。その周囲には小さな「難民村」がいくつも形成されていた。
林氏はヒーローのような心の高ぶりを感じた。「よし、乗り込むぞ」とばかりに難民村に到着。診察を受けようとザワザワと集まる村人たち。タイ人技師が順番にレントゲンを撮り、林氏はフィルムを見て結核や肺炎などの陰影がないかを診断していく。およそ3つの難民村を巡回し、診察するのは1日で90人ほどにのぼった。
難民が暮らすエリアの検問所が閉まるのは夕方5時だ。ランドクルーザーに再びレントゲン装置を載せて、林氏たち3人が住む高床式の民家に戻る。そんな毎日だった。
高床式の民家での暮らしは、林氏にとって理想そのもの。うつも治まった。床下でニワトリが鳴き、庭にハンモックをつるしては昼寝をした。お手伝いの女性が食事などの世話をしてくれる。後輩の医学生が遊びに来ることもあった。